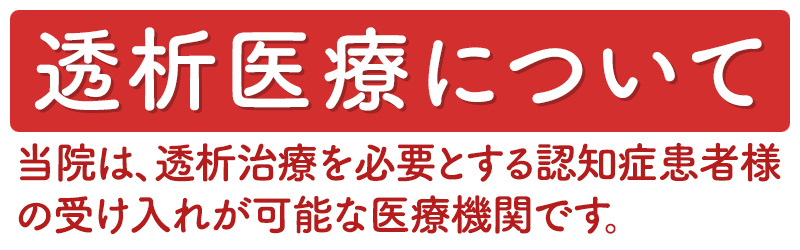
![]()
![]()
このたび当院院長 木川好章が、医療情報紙「メディカル・ビューポイント」に原稿を寄稿いたしました。
寄稿のテーマは「認知症(高度)における身体合併症(特に透析・感染症)の診療について」で、認知症高齢者に対する医療に長年携わってきた経験をもとに、わかりやすく解説しております。
本稿は、医療・福祉関係者だけでなく、地域の皆さまにもぜひご一読いただきたい内容となっております。
現在日本は長寿(2023年平均寿命:男性81.09歳、女性87.14歳)男女合わせて世界1位であり、総日本人口に対する高齢者率は29.6%と超高齢社会を迎えている。
高齢者の特徴として1人の患者が多くの疾患をもつ多病がある。日本の医療では臓器別医療に適応するように整備されており、これは高齢者にとって適しているとは言えない側面もある。
80歳を過ぎると平均して8種類の疾病をもつともいわれている。たとえば、肺気腫の患者が糖尿病で腰痛があり、白内障で骨粗鬆症、また、認知症、皮膚掻痒症であるというように数種類の疾病を抱えるのが普通である。さらに、薬剤の処方、栄養、心理状態、高齢者に特有な症候などの面からのサポートも必要である。
そんななか、当院は認知症(主に高度)に加え、各身体疾病を持ち合わせた患者診療にあたっている。認知症のBPSD、せん妄などの対応に精神科医、また、身体疾病の対応に老年病専門医があたり、二人主治医制をとっている。
コロナ禍においても、コロナに罹患した高度認知症・精神疾患患者の診療(2025年5月末時点にて延入院患者数291名、延外来患者数7,206名)にあたっている。
2011年の東日本大震災時には、被災された認知症の透析患者を受け入れ、診療に従事してきた。
近年、透析の患者導入年齢は高齢化しており、透析導入後に認知症を合併してくる患者も認められる。そのため、メンタルヘルスケアの必要性が高まっている。主な精神症状として抑うつ症状・不安・怒り・攻撃性・不眠・行動の問題・せん妄が挙げられる。これら精神症状にて精神科医の介入の必要性を考え、当院では二人主治医制に努めている。今後、災害発生時に課題がある。透析医療は大量の水道水・電気の安定した供給が保障されて初めて成り立つ医療であり、災害時には特に脆弱と言える。そのため、地下水による水の確保・自家発電機・ソーラーパネル設置に加え、透析認知症患者のネットワーク構築に努めている。